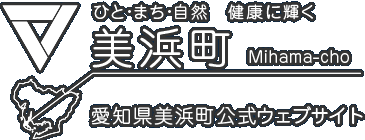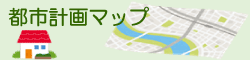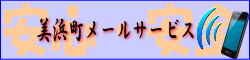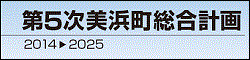公開日 2024年04月22日
被保険者の方が医療機関で受診するときは、医療費の一部を自己負担することになります。
医療費の一部負担割合の区分
病院の窓口で国民健康保険被保険者証などを提示することにより、下記の自己負担割合で診療を受けることができます。
| 区分 | 自己負担割合 | |
|---|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 | |
| 義務教育就学後から70歳未満 | 3割 | |
| 70歳以上75歳未満 | 一般・低所得者 | 2割 |
| 現役並み所得者 | 3割 | |
- 現役並み所得者とは:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
70歳以上75歳未満の方の医療について
自己負担割合や自己負担限度額が変更になります。自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されますので、お医者さんにかかるときに必ず提示してください。
(注意)高齢受給者証は70歳に達する月の翌月から有効になります。
医療費が高くなったとき(高額療養費)
医療機関の窓口で支払った一部負担金が1ヶ月に自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を国民健康保険から支給する制度です。
ただし、医療機関等にお支払された日の翌月1日から2年で時効により申請できなくなります。
計算対象
暦月ごと(月の1日から末日まで)、医療機関(同じ病院でも歯科や入院、外来の違いがある場合は別医療機関として扱われます)ごと、保険診療分のみが対象
(注意)70歳未満の方については21,000円以上の自己負担額が発生したもののみが計算対象となります。
申請に必要なもの
- 役場から郵送された高額療養費の申請書
- 預金通帳または振込先が確認できるもの
- 被保険者証および高齢受給者証(70歳以上)
- 申請に来られる方の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
- 世帯主および受診された方の個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの
自己負担限度額
70歳未満の自己負担限度額(月額・世帯単位)
| 区分 | 所得 | 3回目まで | 4回目以降 |
|---|---|---|---|
| ア | 旧ただし書き所得 901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 旧ただし書き所得 所得600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 旧ただし書き所得 所得210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 旧ただし書き所得 所得210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 旧ただし書き所得とは:総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額です。
- 所得の申告がないと、自己負担額は最も高い金額で計算されます。
- 限度額4回目以降とは:同一世帯で高額療養費に該当する月が、過去12か月に4回以上あるときは、4回目からは自己負担限度額が引き下げられます。
- 住民税非課税世帯とは:同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯のこと。
70~74歳の自己負担限度額(月額)
一般・低所得者:個人単位で「外来の限度額」を適用します。世帯で「外来の限度額」も合わせ、「外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額」を適用します。
(注意)70歳に達した月の翌月からこちらの限度額となります。
| 所得 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%【140,100円(注2)】 | |
| 現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%【93,000円(注2)】 | |
| 現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円(注2)】 | |
| 一般 | 18,000円(注1) | 57,600円【44,400円(注2)】 |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 現役並み所得者3とは:同一世帯に住民税課税標準額が690万円以上の70~74歳の国保加入者がいる方。
- 現役並み所得者2とは:同一世帯に住民税課税標準額が380万円以上690万円未満の70~74歳の国保加入者がいる方。
- 現役並み所得者1とは:同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上380万円未満の70~74歳の国保加入者がいる方。
- 低所得者2とは:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1を除く)。
- 低所得者1とは:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得から必要経費、控除を差し引いたときに0円となる方。
(注1) 年間(8月から翌年7月)の限度額は、144,000円です。
(注2) 過去12か月以内に、高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は【】内の限度額になります。
70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯の場合の高額療養費計算の流れ
1.70歳以上の方の外来の一部負担金について個人単位での計算をします。
2.70歳以上の方の入院分と1.の計算後の外来分を合わせた世帯単位の計算をします。(ここまでは70歳以上の限度額区分で計算します。)
3.70歳未満の方の高額療養費の対象となる一部負担金と2.の計算後の70歳以上の方の一部負担金を合わせて、70歳未満の限度額区分での計算をします。
75才到達月の患者負担の限度額の特例
国民健康保険の加入者が75才になって後期高齢者医療制度に移る場合または社会保険の加入者が75才になってその配偶者が国民健康保険に加入する場合は、その月の自己負担限度額は通常月の2分の1になります。
入院したときおよび高額な外来診療を受けるとき
限度額適用認定証について
限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、保険内診療分につき一医療機関ごとで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
認定証は原則申請日の属する月の1日から有効となりますので事前に申請してください。なお、保険税を滞納している人は原則、認定証の交付は受けられません。また、現役並み所得者3の方および一般の方は、「高齢受給者証」を提示することで、自己負担限度額におさえることができますので、申請は不要です。
様式第16 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書[PDF:33.6KB]
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すると限度額適用認定証の事前申請は不要です!!
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、限度額適用認定証の事前申請は不要となり、窓口での支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
詳しくは以下厚生労働省のホームページやリーフレットをご確認ください
マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)
【リーフレット】マイナ保険証をご利用ください[PDF:668KB]
入院時の食事代と差額申請について
住民税非課税世帯の方においては入院時食事療養費の標準負担額(65歳以上で療養病床に入院される場合は入院時生活療養費の食事代)が以下の表の金額に減額されます。
| 負担区分 | 食事代(1食につき) | ||
|---|---|---|---|
| 令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | ||
| 住民税課税世帯 | 460円(注意) | 490円(注意) | |
| 住民税非課税世帯 低所得者2 |
過去1年間で90日までの入院 | 210円 | 230円 |
| 過去1年間で90日を超える入院 | 160円 | 180円 | |
| 低所得者1 | 100円 | 110円 | |
(注意)指定難病、小児慢性特定疾病の患者の方は、1食につき、令和6年5月31日までは260円、令和6年6月1日からは280円。
食事差額の申請
食事代が減額される方について限度額適用・標準負担額減額認定証を提示せずに入院された場合や入院日数が90日を超えた場合などに減額されていない金額で食事代を支払った部分について、差額支給の申請ができますので以下の書類を住民課国保年金係の窓口にお持ちください。
- 領収書(入院期間および食事代のわかるもの)
- 預金通帳または振込先が確認できるもの
- 被保険者証および高齢受給者証(70歳以上)
- 申請に来られる方の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
- 世帯主および受診された方の個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの
高額療養費の外来年間合算について
支給対象及び計算方法
基準日(毎年7月31日)において、高額療養費の自己負担限度額の所得区分が「一般」または「低所得者」の70~74歳の方が対象です。
計算期間(前年の8月1日~7月31日)における外来診療の自己負担額が、年間上限額(144,000円)を超える場合に、その超えた分が支給されます。
ただし、計算期間において、月毎の高額療養費の支給を受けることができる場合は、その支給額を除きます。
申請に必要なもの
- 役場から郵送された申請書 (基準日に美浜町国保に加入している方で、美浜町国保での外来診療分が年間上限額を超える場合は、役場から12月下旬以降に申請書を世帯主の方へ送付します。)
- 預金通帳または振込先が確認できるもの
- 被保険者証および高齢受給者証(70歳以上)
- 申請に来られる方の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
- 世帯主および受診された方の個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの
注意事項
- 申請できる期間は基準日の翌日(期間中に死亡された場合は死亡日の翌日)から2年以内です。
- 対象計算期間中に、医療保険の異動があった場合は、異動前の医療保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けた後、申請書に添付してください。
- 計算期間中に、美浜町国保から他の医療保険へ異動された場合は、申請により「自己負担額証明書」を交付します。基準日時点で加入している医療保険者に自己負担額証明書を添えて申請してください。
一部負担金の減免等
災害等により重大な損害を受けたり、収入が著しく減少したことにより、資産・能力の活用を図ったにもかかわらず生活が困難になった場合、医療機関へ支払う入院療養分の一部負担金を免除、減額または徴収猶予する制度があります。詳しくは国民健康保険担当にお問い合わせください。